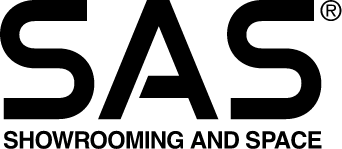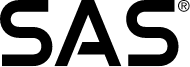伝統文化の永続を目指した着物ブランド「keniamarilia(ケニアマリリア)」
着物市場のピークは1970年代〜80年代前半。ライフスタイルや流通構造の変化から、市場規模はピーク以降縮小の一途をたどっている。
実際に、成人式、卒業式、結婚式など人生の節目で着られている和服だが、日常生活で纏うことはほとんどない。
そんな中、日本文化の永続を目指した着物ブランドが2019年に誕生した。座波ケニア氏による「keniamarilia(ケニアマリリア)」だ。
着物を再構築し日常着に蘇らせる

keniamarilia(ケニアマリリア)のウェアは古い着物からつくられ、着物を一着一着丁寧にほどき、日常使いできる新たなウェアへと蘇らせていく。現在は、シャツ、スカート、ボレロ、羽織などを展開。
使用する着物は、ある程度の耐久性を重視して、着物生産のピークであった1980年代物を中心に、中には100年前の着物が用いられている。

40年以上も前の着物を用いているのに、どの生地も「古さ」を感じないほど綺麗なことに気づく。
工程をうかがうと、ほどいた後の生地は入念な洗浄、防縮、綺麗にプレスしてから、裁断、縫製に入っていくという。時には手作業を加えながら丁寧に下処理がされているのだ。

防縮加工を施す理由は、自宅でも手軽に洗えるようにするためだ。繊細な生地は、防縮加工をしていないと縮みやすく、一反一反美しく描かれた柄もずれてしまう。
カジュアルな日常着として楽しめるよう、手入れのしやすさも考慮しながらつくられている。
着物の文脈に即した生地の選定とデザイン

keniamarilia(ケニアマリリア)は、着物を「日常着」として楽しむことをコンセプトにしているため、古くから「普段使いのおしゃれ着(街着)」として愛用されてきた「小紋柄」を主に使用している。
日常着として馴染みやすい視覚的な観点もあるが、着物文化の文脈をきちんと継承したいという思いが込められた。

その文脈はデザインにも踏襲されている。
例えば、keniamariliaのシャツには縫い目がほとんどない。

着物の和裁では縫い目が基本的に表に見えないようつくられていることから、縫製もその文脈にのっとり二枚合わせの袋縫いという技法が用いられた逸品だ。

そして通常は、穴を開け淵を刺繍してつくられるボタンホールだが、keniamariliaのシャツは模様をさえぎらないよう着物に穴をあけることなく、また仕上がったときの手触りを考慮し、シームレスな縫製を施した。

もちろん製作工程は膨らみ、縫製を請け負える工場も限られていくが、日本の美的感覚を損なわず作品をつくることに重きをおいている。
一点物をオーダーメイドできる、SAS®で初の試み
X(エックス)では、ブランドを立ち上げる前から伝統文化についての発信を続け、noteでは自身のブランドの背景や商品づくりなどコンテクストを重視して発信してきた座波氏。数多くのインプレッションと共感を得て、沢山のファンと繋がった。

コロナ禍を乗り越え、ブランド立ち上げから6年目の2025年秋、好きな反物を選んで一着をオーダーできる新しい試みとして、SAS®で先行受注会をおこなった。
約200種類もの反物を用意し、実際に染織の美しさを楽しみながら、まるで呉服店で着物を誂えるような特別な空間を提供した。
反物を身体にあてて、自分に合う着物をじっくり吟味できる贅沢な時間。

繊細に織られている模様は、光の当て方によって色合いが変化して見える。実際に身体にあててみると、予想外の柄や色が自分にとって顔なじみよかったり、唯一無二の出会いに高揚するひとときだ。
(画像の文様は、破れ亀甲。亀の甲羅を模した亀甲文様を、連続したパターンでなく途切れさせたり一部を省略をしたり、文様に変化とリズムをもたらしている。亀甲が欠けているのは、不完全なものを愛でる日本の感性や、魔に魅入られない縁起物などの意味合いがある。)
keniamariliaが目ざすのは着物文化の永続
サンパウロで生まれ、4歳で日本に移住した座波氏。
幼い頃から着物に親しみはあったが、成人式で振り袖を纏ったことを機に着物の美しさに惚れ込んだ。
アパレル業界で積んできたキャリア
幼少期からファッションに親しみ、ファッションデザイナーを目指していた彼女は、服飾専門学校を卒業した後アパレル企業に就職。営業、企画デザイナー、生産管理などアパレル業を一通り経験する。
その後フリーランスとして独立し、企業やブランドのサンプル縫製、アーティストの衣装製作などをおこない、2019年に自身初のブランド「keniamarilia(ケニアマリリア)」を立ち上げた。
なぜ着物ブランドを立ち上げたのか?
振り袖を纏った時に感じた、着物の美しさ。そして伝統の重み。同時に着物産業が衰退している事実を知り、業界に貢献する気持ちが芽生えたという。

外国籍の自分が日本の伝統文化である着物を扱うことに葛藤はあった。しかしアパレル業界では、生産現場で工場がなくなってきているのを見てきた。
「振り返った時にはもない」という現状を目の当たりにしてきたからこそ、手遅れになる前に行動することが先んじたという。
新しい需要と文化構築、その先の発展を目指して
「伝統産業や文化の継続には、守る部分はしっかり守って、新しい価値、重要を構築していくことだ」と座波氏は考える。

現在は、眠っている着物を現代に呼び戻し、日常着として楽しめる和服のニュースタンダードを構築しているところだ。
日々触れることによって、着物を着るきかっけを創出し、業界を底上げしていくことを目指し、そして日本国内にとどまらず、着物を世界に届け、発展をさせることをブランドのミッションにして活動している。